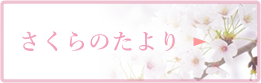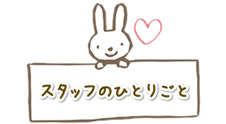未成年のお子さんがいる場合には、離婚の際、親権者を決める必要があります。
親権者を決めるに当たっては、子どもに対する愛情の度合い、これまでの養育実績、今後の監護に対する意欲、子どもの面倒をみるための時間的余裕、生活環境、経済力、実家からの支援、子どもの年齢、子どもの意思など、あらゆる事情を考慮して判断されます。
特に重視されるルールとしては以下のものがあります。
①継続性の原則
これまで現実に子どもの面倒を見てきた親を優先させるという考え方です。現在の環境で安定している親子関係を変化させることは、子の情緒を不安定にするため好ましくないという配慮です。
②子の意思の尊重
家事事件手続法は、子どもの意思を把握し、子どもの年齢・発達の程度に応じて考慮しなければならないと定めています。ただし、子どもの意思を最優先に親権者が決定されるわけではありません。あくまでも一要素として考慮されるとされています。
「子どもが母親(父親)の方がいいと言っている」という主張はよくなされますが、子どもはどちらの親にも気を使いますので、一方の親に尋ねられれば、その親が喜ぶような発言をします。ですからそのような主張をしても簡単には採用されませんし、またこのような質問を親から子にすること自体、適切ではありません。
親権が激しく争われる事件では、裁判所の調査官が介入し、お子さんの意思を把握する調査が行われています。
③兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹は分けないのが望ましいと考えられています。親の都合で、これまで一緒に育ってきた兄弟姉妹を失うのは子どもにとって不幸なことですし、また子どもは「親権者にならなかった親は自分のことをいらないと考えたのだ」「自分は選ばれなかった」という疑念に陥りがちです。
離婚による子どもの不幸が少しでも軽減されるよう、夫婦双方が冷静になって話し合う必要があります。
④母性優先の原則
過去の裁判例では母親による監護が望ましいとされてきましたが、父親が子育てにかかわる例や、共働きの家庭が増えてくるにつれ、今後は単に母親であるという理由だけで優先されることはなくなっていくと思われます。
ただし、母親がそれまで子どもの世話を主に看てきたケースであれば、母親が親権者に指定される可能性が高いと言えます。
なお、収入が多いか少ないかは、親権者を決定する材料にはなりません。収入が少ない方が親権者に適しているのなら、収入が多い方が養育費を支払えばよいからです。
親権の解決事例