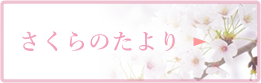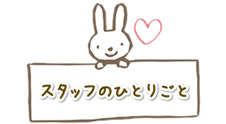1 年金分割とは
夫婦の一方が多く厚生年金(共済年金)の保険料を支払っている場合に、夫婦の年金保険料納付実績を分割して、当事者の公平を保つ制度です。
将来支払われる年金を分けてもらえるのではありません。
分割されるのは年金保険料の納付実績であり、実際に年金がもらえるかどうかは、年金受給年齢に達したときに受給資格を満たすかどうかによります。
例えば、夫だけが会社員として厚生年金保険料を納めている場合、専業主婦の妻は将来厚生年金を受け取れません。そこで、離婚時に年金保険料の納付実績を分割し、妻も厚生年金の保険料を納めてきたという実績に変更することができます。
夫婦が同額の年収をもらって年金保険料を納めていたケースや、双方が自営業(国民年金)で働いているケースでは、分けるものがありませんので年金分割は不要になります。
2 年金分割の方法
①合意分割
平成19年4月以降、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、年金分割を受けられるようになりました。この制度を「合意分割制度」といいます。分割割合は、最大0.5(2分の1)です。
②3号分割
平成20年4月の制度変更で、妻が被扶養者であった期間の年金情報を分割できるようになりました。この制度を「3号分割制度」といいます。当事者間の合意も、裁判所の決定も必要なく、年金事務所に届出をすることによって分割できます。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみですので、それ以前に分割期間が存在する場合にはこの制度で分割することはできません。
3 時効
離婚が成立した日の翌日から2年が経過すると年金分割を請求することはできなくなります。
2年以内に年金事務所へ届出が必要ですのでご注意ください。