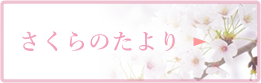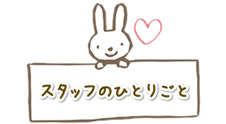1 面会交流とは
面会交流とは,親権者とならなかった親が子どもと交流する機会を言います。
離婚してもお子さんのことについては協力し合える夫婦であれば、特に面会交流について具体的に決めておく必要はありません。
しかし、離婚後に連絡をとることでトラブルになりそうな場合や、親権者になる予定の配偶者が面会を拒絶している場合には、あらかじめ面会の方法や回数を協議して決めておくのが良いでしょう。
2 面会交流の方法
面会の方法に決まりはありません。
月に1回程度、直接会って面会するのが一般的ですが、離婚後も近くに住むのであれば、学校帰りに親権者でない親の家に寄って会うという方法でも構いませんし、遠方に住むのであれば夏休みや冬休みにまとめて宿泊面会をする方法もあります。
日程を合わせるのが難しいのであれば、動画や画像などを送ったり、オンラインや電話を利用した間接面会の方法も考えられます。
お子さんが大きいのであれば、親権者でない親とお子さんとの間で連絡を取り合って会うということでも良いでしょう。
3 面会交流について協議がまとまらないとき
協議がまとまらない場合,家庭裁判所へ面会交流調停の申立を行います。
調停でも合意できない場合には、裁判所が審判手続を経て面会交流の方法を決定します。
4 面会交流が制限される場合
面会交流は実施するのが原則ですが、以下のような場合には制限される場合もあります。
(1)非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合
子供に対するDVがあるケースや、面会のルールに違反し,今後も違反が繰り返される可能性が高いケースでは、面会が制限される場合があります。
(2)夫婦間の精神的対立が激しく,子どもの精神的安定を阻害する場合
以前は親権者(監護親)が強く面会を拒否している場合には面会を制限する裁判例が見られましたが,最近では、親の都合で子どもが片親を失うことのないよう,面会交流に対し積極的な判断が主流となっています。
(3)子どもの意思
面会を実施すべきかどうかの判断には、子どもの意思が考慮されますので、子ども自身が強く面会を拒否している場合には、面会が制限される場合があります。ただし幼児期の子どもは、監護親の意見に影響されやすく、夫婦の紛争の影響を受けやすいので、子どもの意見だけを理由に面会が制限されるとは限りません。
5 まとめ
離婚を争っている当事者は「あんな親なら、いない方が子どもにとって幸せ」と考えがちですが、子ども自身にとっては親であることに変わりありません。
自分の知らないところで親権者や面会交流について決められた子どもは,「自分は捨てられたのではないか」と悩むこともあるでしょう。
そのようなことにならないよう,親権や面会交流については,夫婦双方が冷静になって話し合うことを心がけましょう。
面会交流の解決事例