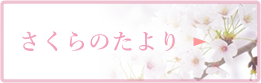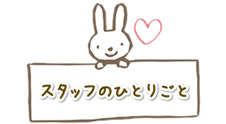厚生省労働省のデータによると、国内の年間離婚総数は,1990年に約15万件であったものが,2000年には約26万件まで増加しました。
厚生省労働省のデータによると、国内の年間離婚総数は,1990年に約15万件であったものが,2000年には約26万件まで増加しました。
このうち中高年(50歳以上)の年間離婚総数は約2万件であった1990年から,2000年までの10年間で約2.5倍の5万7000件に急増し、2010年には約6万2000件まで増加しています。
中高年の離婚件数が増加をした背景には、大きく二つの要因があります。
1.団塊の世代が中高年をむかえたこと
高度経済成長期に結婚をした世代(いわゆる“団塊の世代”)が、中高年になり、子どもの成人や夫の退職を機に離婚をするというケースが多く見られます。特に女性にとって、結婚当時は、男女の社会的な役割分担が明確にされており、夫に尽くすのが当たり前で,長年我慢を強いられてきたということがあります。
しかし男女の役割分担に対する社会全体の意識変化に伴って,家庭内での役割を終えたのを機に,離婚して新たに人生をやり直したいという女性が増えているものと考えられます。
2.年金制度の改正
2007年に年金分割制度が改正されたことも中高年の離婚件数の増加の原因となっていると考えられます。
従来は「年金は夫婦であっても別々のもの」と考えられており,妻が専業主婦,夫が会社員という一般的な家庭のケースでは,夫しか厚生年金を受け取れませんでした。しかし法改正により,夫の厚生年金の保険料納付実績が妻に分割されることになったため,これにより離婚後の経済的な問題が軽減されたことも中高年の離婚への弾みとなっているものと思われます。
離婚のポイント

中高年の離婚にとって最も重要なポイントは,”離婚後の生活をどのように維持するか“ということです。
労働収入が得られる期間は限られているため,婚姻期間中に形成した資産をどのように分配するか,また年金を受け取れるかは最重要ポイントになります。
特に,家計にとって大きなウェイトを占める住居費をどのように賄うかは考えておかなければなりません。若い世代の離婚では,妻が実家に帰って両親と同居するケースが多いですが,中高年の場合,実家は既に別の兄弟が跡を継いで暮らしていたり,空き家となっていて生活できる状態にするのに相当な費用を要したりなど,実家を当てにできないのが一般的です。このため自宅不動産は,夫婦のどちらにとっても必要不可欠なケースが多く,老後の生活を維持するために自宅を取り合うことになる場合があります。
また,退職金をどのように分配するかも重要です。退職金を財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、取得するであろう退職金額から計算をし、分割してもらうことができます。しかし、退職金の取得がはっきりしない場合には、財産分与として認められないケースがあります。
これらの計算や立証、主張の組み立ては複雑な面がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお奨めいたします。立証のための証拠の収集のみならず、話し合いで成立させられる場合には、離婚協議書の作成や調停証書の作成をいたします。